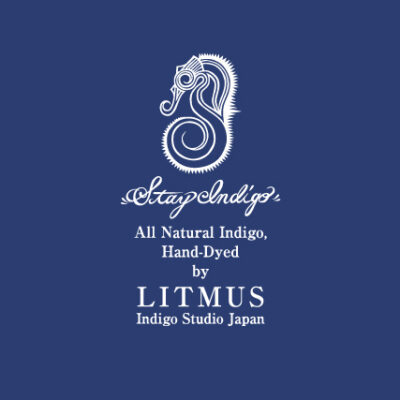日本酒と藍染 -LITMUSさんの酒蔵見学
酒造りと藍染。それは共に醗酵の力を駆使した日本の伝統文化といえるでしょう。今号の表紙作品をお願いしたのは、海風薫る鵠沼で日本古来からの「灰汁醗酵建て(あくはっこうだて)」という染色技法による藍染を続けるLITMUS(リトマス)さん。ワイルドな風貌で藍染を熱く語る吉川さんと、ソフトな印象の中にも芯の強さを併せ持つ松井さん。化学薬品には一切頼らずに天然の素材で自然の醗酵を促しジャパンブルーと呼ばれる藍色を生み出す二人組です。

LITMUS 吉川和夫さん(左),松井裕二さん(右)
リトマスさんとの出会いは今から14年ほど前に遡ります。共通の知人を通して蔵元の自宅を吉川さんが訪れたことが始まりです。日本の伝統文化である藍染の技術を継承しつつ自分達の感性で現代の若者にも藍染の素晴らしさを広げたいと熱く語る吉川さんと意気投合した蔵元。ちょうどその頃オケバ開業に向けて準備を進めている時期で、是非リトマスの作品をオケバに置いて欲しいとお願いしたところ、快諾いただいたのがきっかけです。以来リトマスファンとしても応援を続け、また共感する感性は色々なご縁を繋ぎ、家族ぐるみのお付き合いが続いて います。

okebaでは常設の他、毎年「LITMUS」展を開催。

醗酵特集である今号、リトマスさんならどんな作品で表紙を飾ってくださるのかワクワクしていたところ、改めて酒造りをきちんと理解しておきたいということで蔵見学に来てくださいました。酒造り真っ最中の凍つく12月の蔵で、蔵元の話に熱心に耳を傾けるお二人の手は、藍で染まり爪まで真っ青。Tシャツ一枚一枚の染めにもこだわるお二人は、仕上がり具合を正確に把握するためにあえて手袋はせず素手の感覚を大事にしているそう。その手は藍染を愛し真摯に向き合っている証のようで、圧倒的な迫力さえ感じさせるものです。

爪まで藍に染まる職人の手
さて、酒造りと藍染という、一見なんの関係もなさそうに見える二つの世界。しかし藍染は草木染めの中でも、醗酵した藍液で染め上げる伝統技法です。生み出される物は全く違うけれど、醗酵による微生物の力を最大限に引き出すために人間が手助けしていくという点では共通しています。長年の経験に基づいた徹底した温度管理と緻密な計算、そして何より愛情が美味しいお酒、良い藍液を育てるのです。そして驚いたことに、リトマスさんでは藍液の醗酵を促すための糖分として、小麦ふすまと日本酒が加えられるそうです。酒造りも藍染も、生き物である菌を育てコントロールすることが肝要な伝統文化であることを再認識させられます。
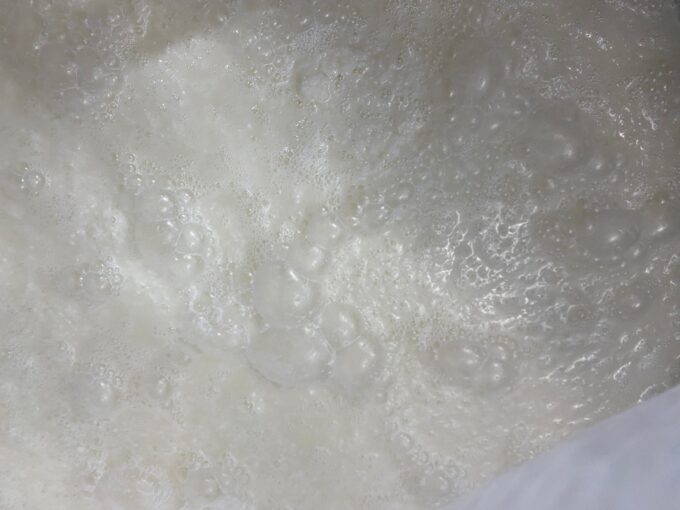
醗酵する酒母

醗酵が進んで泡立ち始める藍の華
酒造りの工程や道具を興味深く見学されたお二人。 
酒造りは理想の味を決め、それを目指して逆算して作業をすすめていくという蔵元の言葉に対し、藍染はできた藍液の状態を見極めて、その中で最大限力を引き出せるよう染めていくという点で、より感覚的で原始的かもしれないと感想を述べられたリトマスさん。一方、大量生産のための化学薬品を使わず、自然の力で醗酵を促して少量でも質の良い作品作りにこだわる彼らの姿は、我々が目指す酒造りへの向き合い方と共通しています。お互いの技術や考え方の相違点が理解でき、形は違えどモノづくりに懸ける熱量は同じだと大いに盛り上がった蔵見学となりました。

藍の初仕込み用の酒のチェック
そして、酒造りの際にタンクの醪(もろみ)をかき混ぜる櫂棒が、藍液を混ぜるのにも最適そうということで、2022年藍液の新年初仕込みの際には蔵元が櫂棒と天青の純米酒を携えてお邪魔することとなりました。それはまるで、ジャンルを越えて交わされた契りのようで、これからも醗酵し、じわじわと熟成していくであろうお互いの関係を物語っているようでした。
LITMUS工房にて藍染の仕込みレポ

工房に入るとあずきを炊いたような良い香りと冷えた空気が混ざり、そこに古い家屋の趣が空間に厚みを加える。あずきの香りの正体は、小麦のカラ「ふすま」を灰汁に混ぜドロドロに炊いたもの。これを微生物に食べさせて醗酵を促すのです。染料である「すくも」に「ふすま」を加え、ここに他の糖分として日本酒を入れます。蔵元が言うには「お酒を入れるのは神頼みや儀式的な要素など、糖分以外の理由もありそうだね。」それだけ藍染の微生物とのやりとりが、1+1=2ではいかない繊細さを持つということ。適度なpH値を維持するための素材の質へのこだわり。クヌギやナラの燻製の灰、質の良い「すくも」(藍の乾燥葉を醗酵させた染料)を吟味して使っています。
 この「すくも」は醗酵すると土のような状態になり、これを灰汁と混ぜて藍染液を作ります。この工程を「藍建て」と言います。「藍を建てる」という言葉は正確には由来ははっきりしていないのですが、LITMUSでは「微生物にとってそこが我が家のように、心地の良い環境になるように」という想いを含んで藍を建てていると言います。
この「すくも」は醗酵すると土のような状態になり、これを灰汁と混ぜて藍染液を作ります。この工程を「藍建て」と言います。「藍を建てる」という言葉は正確には由来ははっきりしていないのですが、LITMUSでは「微生物にとってそこが我が家のように、心地の良い環境になるように」という想いを含んで藍を建てていると言います。

藍の甕の初仕込み! 微生物の栄養となる日本酒を投入。
そんなちょっと緊張感も漂う神聖な初仕込み。蔵元が持参した日本酒をまず一献口に含み味わいを確認してから、先ほどの「ふすま」と「すくも」を加えた藍甕の中に投入します!「神主になった気持ち」と、ちょっとほろ酔いなのか漏らす蔵元。ここから過醗酵になったりしないように安定した染料づくりがはじまるのです。染液は空気に触れて青色に発色するので、今の状態はすくもの茶色い状態。表面のモコモコしている部分は黒光りしたメタリックな色合いで、こころなしかキラキラ輝いて見えました。微生物が食事を愉しんでいるのかもしれません。これがあの、空のような清々しい青にものを染めていくなんて、不思議なものです。

自然界のもので青を持つものは少なく、藍は微生物の醗酵によりその色を出します。その技法は難しく青色は高級品であったにもかかわらず、日本では江戸時代藍染の最盛期をむかえます。各地で藍染の染色技法が発展しLITMUSは現在そのひとつを継いでいる感じだと言います。温度管理が大変重要で、試行錯誤で歴史と現在の状況を鑑みて染師の仕事をこなしています。薬品などを使った簡易的な染の商品が流通し、真摯に向き合い手間ををかけて作られた染料も貴重とされる昨今、人間と微生物のやりとりを大事にし「どこまで安定した染め液づくりができるか」というところに挑戦し続けるLITMUS。目に見えるものだけが確かな存在ではない、目に見えないものの働きこそ未来への足掛かりなのではないかと、醗酵つながりということであらためて考えさせられました。

ちなみに現在順調に醗酵を続ける染液ですが、「いつもよりモコモコしている気がします。」と嬉しいお言葉を頂きました。